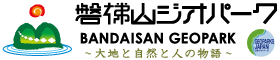天鏡台は磐梯火山が噴出した溶岩により形成された台地である。天鏡台付近にはかつて溶岩が広く露出していた。現在では露出はわずかであるが、緻密で黒い基質の中に白色の斜長石が斑点状に含まれ、安山岩の特徴をもっている。
 天鏡台溶岩
天鏡台溶岩磐梯火山はおよそ30万~40万年前に誕生し、溶岩などを噴出し山体を成長させてきた。磐梯火山は大きく先磐梯期と古磐梯期と新磐梯期の3つの活動時期に分けられる。先磐梯期の活動による地形は明瞭には残っていない。赤埴山と櫛ヶ峰が古磐梯期の活動により形成された山体で、主峰である大磐梯や1888年の噴火で崩壊した小磐梯が新磐梯期の活動で形成された山体である。
 磐梯山遠望
磐梯山遠望古磐梯期の山体が形成された後、3~5万年前に起こった噴火で山体が崩壊し翁島岩なだれが生じた。その後崩壊した部分に、溶岩の噴出により大磐梯を中心とした新磐梯期の山体が形成された(図1)。天鏡台の溶岩は新磐梯期の溶岩のひとつでおよそ3万年前に形成されたものである。
 磐梯山の地質図(千葉・木村(2001)をもとに作成)
磐梯山の地質図(千葉・木村(2001)をもとに作成)