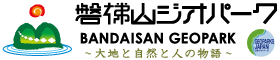柏木城跡は、会津盆地北縁・標高512mの丘陵上に所在し、1583年(天正13年)、桧原に侵攻した出羽・米沢の伊達氏に対抗するため、会津の蘆名氏により整備された戦国時代の山城である。城跡の北側には、会津と米沢を結ぶ近世の米沢街道が走り、戦国時代においても両地域を結ぶルート(ここでは「米沢路」と称する)として存在していたと考えられる。
城内に残る石積
柏木城跡で特徴的なのは、主郭曲輪群に普請された石積みである。石積みは発掘調査以前より城内の一部で露出しており、土造りの山城が一般的とされる東北地方戦国時代の山城としては稀な事例として注目されていた。発掘調査の結果、主郭内を区画する土塁や、主郭の周りに造られた土塁の内側、さらに主郭へ向かう通路や出入口(虎口)でも石積みが確認された。現在、土塁上に残る石列の分布状況を踏まえると、石積みは主郭曲輪群にある土塁の内側ほぼ全体に普請されていると推定される。また「虎口1」には、織豊城郭の虎口で見られる「鏡石」に似た特徴を示す大きな平たい石も据えられるなど、石積みには多彩な種類があり、大規模に石積みが施されている様子から、柏木城跡が“石造りの山城”ともいえる内容を有していることが明らかとなった。土造りの城が多かった会津では、柏木城を見せることで、家臣や領民などに武威を示し、戦意を高揚させていたのかもしれない。なお、石積みに使用された石材については、ほぼ安山岩とみられ、雄国山・猫魔山の噴火に伴う溶岩を起源とする石材であると思われる。
遺構配置
柏木城跡は、城全体の中心となる主郭と城番の居住空間とみられる曲輪2およびその周辺からなる主郭曲輪群を中心に、東側には防御・攻撃双方を考慮した馬出曲輪群がおかれる。主郭曲輪群は戦国最先端の技術である石積と複雑な形状の虎口を有している。東側の馬出曲輪群は、連動するように堀ほり切きりや竪たて堀ぼり、土塁が配され東側からの伊達政宗勢の侵入を強く意識した配置となっている。
その一方、前述の「米沢路支道」は、堀や土塁のために遮断性があるとともに、馬出曲輪群から十分に監視し攻撃できるような造りになっている。これは防御力を高める工夫であると同時に小規模な人数の往来は確保する考え方を読み取ることができる。また、主郭の北・西の山麓には平場群が確認され、会津側の兵が駐屯する空間の可能性がある。
国指定史跡 柏木城跡
柏木城跡は東西500m、南北450mの城域で遺構の残りがよく、石積を多用することや、複雑な虎口を有するなど、戦国期の最新の技術を採用していることも確認されている。せまりくる伊達政宗勢を迎撃するため地形を活かして配した馬出曲輪群は、当時の南東北において蘆名氏伊達氏という二大勢力の抗争を具体的に示す遺構である。
また米沢路を城内に取り込むことにより城に「関所」的な意味合いを持たせたとみられることや、主郭曲輪群の区画や虎口・通路の壁面内へ石積を大規模に普請することなどからは、領国境目での軍事拠点のあり方や、家臣・旗下・領民への示威行為等の具体像を知ることができる遺跡として2022(令和4)年3月15日、国史跡に指定された。