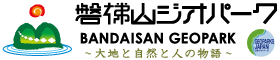大塩虚空蔵堂
大塩虚空蔵堂
大塩字虚空蔵地内に所在する大塩虚空蔵堂については、江戸時代に編纂された会津藩関係の地誌『新編会津風土記』に当時の状況が記されている。
「虚空蔵堂は村から北東に8町(約870m)進んだ山の中腹にあり、四間四方の建物である。虚空蔵座像の長さは3尺(約90cm)で、立岩虚空蔵といい、開基の年月は不明である。御堂の西北に立岩という10丈(約30m)あまりの岩山があり、蒼々とした松が生え、珍しい眺めである。下には岩穴があり、東南に向かい、口の広さは2間(約3.6m)ほどである。本尊は元々この岩屋の中に安置され、拝殿も桟閣の建物であったという。修験の喜福院が管理していた」と記されている(一部省略、現代語訳)。
大塩虚空蔵堂は、山腹の岩場に立地することもあり、修験などの行者が造立に関わったのかもしれない。
現在の虚空蔵堂は、『会津寺院風土記(猪苗代・北塩原編)』によると、1789年(寛政元年)に再建されたと記されている。大きな岩山は現在もあり、下部の岩穴には石仏が安置されている。
この岩は、およそ1500万年前に堆積した五枚沢川層に貫入した流紋岩からなるもので、柱状節理が発達している。流紋岩の貫入岩体は硬質なため、しばしば周囲から突出した地形を形成する。
 岩穴に安置された石仏
岩穴に安置された石仏